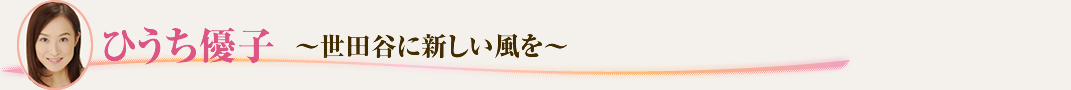
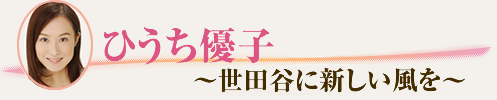
【保育】記事一覧
【令和7年 第3回定例会 決算委員会4】
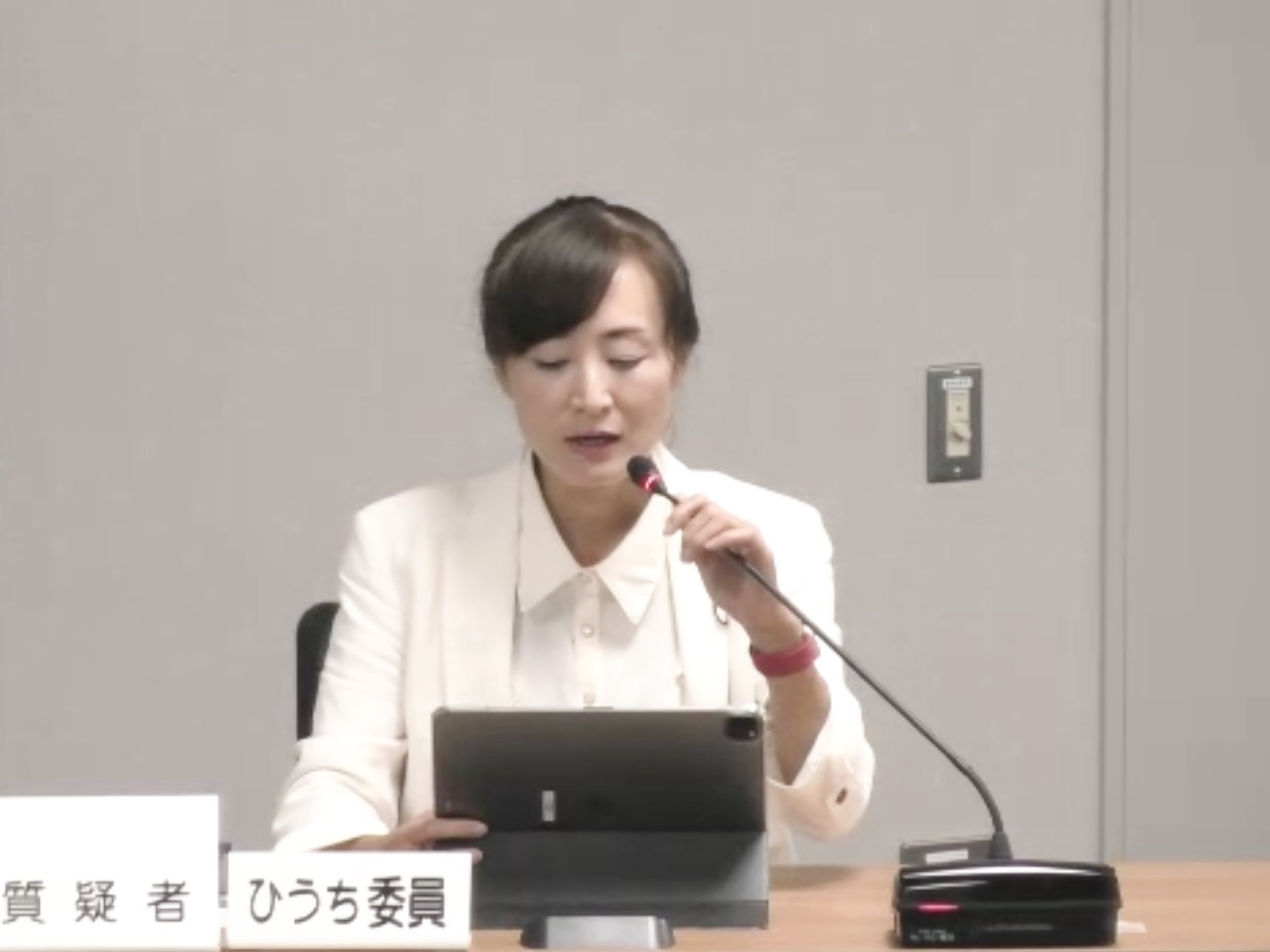
福祉保健委員会の質問です。
ベビーシッター利用支援事業は、ニーズがかなり高く、3月に質問した内容。実現予定でいよいよ始まります!
●就活支援センターの開設について
・行政書士等の専門家との連携体制
・高齢者終身サポート事業への助成制度の創設
● 東京都ベビーシッター利用支援事業の導入について
→実現!!
・世田谷区独自研修の実施と受講結果の公表、見守りカメラの助成が安全確保策として特に有効。見守りカメラ助成の推奨を!
ベビーシッター利用支援事業の導入に向けて、前進‼️
予算委員会で質問した、『ベビーシッター利用支援事業 の導入』。
これは東京都の事業で、ベビーシッターのニーズはかなり高いのに、23区中世田谷区だけが導入していません。
先日の子ども・若者施策推進特別委員会の陳情で、趣旨採択になりました。
いよいよ、導入に向けて、動き出します❗️
乞うご期待!
令和7年 予算委員会 総括質疑
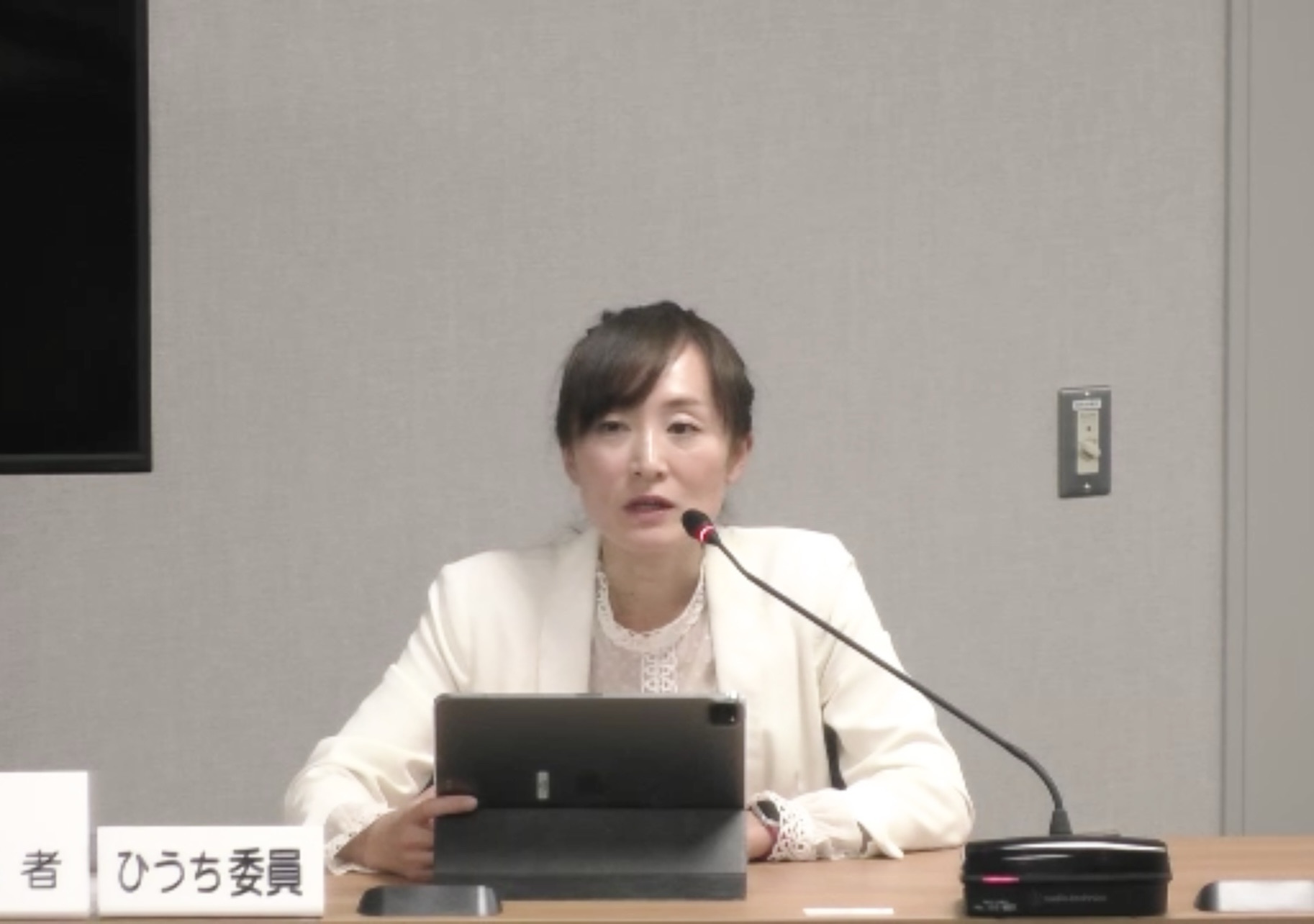
総括質疑では、2テーマ
⚫︎小中学生への自転車の標識教育
⚫︎東京都ベビーシッター事業への参入
簡潔にまとめます。
総括質疑
⚫︎小中学生への自転車の標識教育
質問
自転車は軽車両。標識が適用される。しかし、車の運転免許を持っていない小中学生は標識を学ぶ機会がない。
例えば、
・道徳の授業やホームルームの時間等を活用しての周知徹底
・学校の廊下への標識の掲示
・区立中学校の生徒手帳への標識の記載
・学級通信における標識クイズの実施など実施すべき。
→実現!
・小1、中1で標識のクリアファイルを配布済。
・長期休業日前の生活指導の内容に、ヘルメット着用と合わせて道路標識の指導も含めていく。
・ 廊下への標識の掲示を検討する。
⚫︎東京都ベビーシッター利用支援事業への参入
質問
・「東京都負担100%の東京都ベビーシッター利用支援事業」を世田谷区でも導入すべき。
・この制度は,東京都の認定事業者において,無料でベビーシッターを利用することができる制度。利用できる時間数の上限はあるものの、「保育認定」が不要で事前の区市への手続きも必要もない。
・23区中、19区が導入。
・導入済みの港区では、人気の施策である故に、都負担利用条件に加え、区独自で対象児童の年齢を5歳から小学6年生まで引き上げ、且つ、来年度は区の予算で追加助成の予定。
→答弁
・世田谷区で過去に密室における預かりで刑事事件に至った事故を経験し、またこの間認可外保育施設での重大事故等が度重なり、保育の質の確保には不断の努力が必要。現時点で事業実施は難しい。
・全国保育サービス協会や東京都、各事業者とも意見交換等を行いながら、「保育の質の確保」を果たす方策について、当面の課題として研究する。
◎ツインズプラスサポートの支援について
課題
双子のお子様を持つ私の友人から、「120時間の支援を受けられて本当にありがたいのだが、育児サポートなのに保護者が家にいなければいけないと使い勝手がよくない。母親は、上の子のお世話や送迎、買い物、用事を済ますなど忙しく、一人になってほっとする時間が必要。また、通院や買い物の同行、塾や習い事の送迎が不可というところも増え、区が依頼しているシッター会社は全て可能なので、シッターに頼めることをできるだけ可能にしていただきたい。使用時間も9時から17時ではなく、せめて19時か21時まで使えるようにしてほしい。」との声をいただいた。
課題解決に向けた質問・提案
ツインズプラスサポートの支援について、通院や買い物同行、塾、習い事送迎をメニューに加えること、シッター枠の拡大、使用時間の延長、といった、ご意見をできるだけ反映させる形にしていただきたい。見解を伺う。
成果
・ツインズプラスサポートは、東京都の多胎児家庭支援に関する補助を活用しながら、多胎児を育てる御家庭への妊娠期からの支援の充実を図るため、今年度4月より実施している。
・都の補助事業の要件として、ヘルパーが多胎児妊産婦の自宅を訪問し、外出補助や日常の家事育児支援を行っているが、保護者等の不在時の子どもの預かりについては対象外となっている。そのため、保護者等の同行がない保育園などの送迎については支援の対象外となっている。
・サポート内容や利用時間などは、先行実施のさんさんプラスサポート事業に準じており、ツインズプラスサポートについては開始から6か月を経過していることから、利用状況などについては今後検証していく必要があると認識している。
・区では世田谷版ネウボラとして、全ての子育て家庭を対象に妊娠期から切れ目のない支援に取り組んでいるので、今後も育児に関する個々の相談に継続的に対応し、見守るとともに、それぞれの子育て家庭に必要な支援につなげていきたい。
◎保育園、幼稚園の延長保育について
実現!
課題
・「夜まで仕事で、保育園への迎えに間に合わない。」と言う声が多い。
・週3週4で働く方は、保育園には入れない、という現状がある。
課題解決に向けた質問・提案
・幼稚園での預かり保育の拡充により、保育の選択肢を増やすことで、例えば週3から週4に働く方や、また両親ともにフルタイムで働いているが、教育上、保育園よりも幼稚園を希望するといった方々のニーズにも応えられる。
・以前の質問への答弁では、区内58カ所ある私立幼稚園で、保育園並みのフルタイム型の保育を行う幼稚園は7カ所で、そのほか公開されている28園は独自の方法で実施しているとのことだった。その後の進捗状況を伺う。
成果
・保育園と同様の保育時間での預かりが8園、保育時間が比較的短い園が1園の合計9園において、区独自の補助制度による預かり保育を実施している。
・また、国の補助制度を活用し、教育時間の前後に保育を行う事業を3園で実施しており、私立幼稚園でも独自の預かり保育を28園で実施するなど、保護者の多様なニーズに対応している。
・来年度は、区独自の補助制度による預かり保育を、新たに1園で実施するなど、少しずつ実施園が増えている。
◎認可外保育園への補助について
実現!
課題
・認可保育園に入れずに、やむを得ず認可外保育施設を利用している保護者の方がいる。
課題解決に向けた質問・提案
認可保育園に入れずに、やむを得ず認可外保育施設を利用している保護者の方への負担軽減を図るべきと考える。見解を伺う。
成果
・区はこれまで待機児童の多い0から2歳児の保護者に対し、保育室、保育ママ、認可保育所の保育料との差額を補助し、認証保育所と指導監督基準を満たす認可外保育施設は、世帯の収入に応じて4万円を上限に補助を行っている。
・認可と認可外の保護者の負担額の比較は、最も多い階層である世帯収入700万円で試算すると、認可の保育料は月額35700円となる。認証保育所の平均的な負担額は、区の補助を加えても認可と比べ月額約16000円高く、認可外保育施設では約65000円も認可保育所より高い状況。世帯収入によって負担額が異なるが、総じて認可保育園よりも認証及び認可外保育施設の保護者の負担が大きくなっている。
・区としては、令和3年4月に向け、幼児教育無償化の対象を限定する条例の施行、及び0から2歳児の認証保育所の補助制度の見直しを予定している。基準を満たす認可外保育施設の補助制度について、合わせて検討する。
◎保育園の入園関係の手続の電子申請
実現!
課題
・電子申請が遅れている。
・区民の方々が世田谷区に提出する書類は数多くあり、その手続を簡素化、効率化することは、働く世代の方々にとっては特に重要なこと。
課題解決に向けた質問・提案
保育園の入園関係の手続きを電子申請にするべきと考える。見解を伺う。
成果
・他自治体の動向や、来年度に向けて検討している児童手当の支給等に関する電子申請の導入実績等を参考に、現在、保護者から提出していただいている入園、在園手続等に必要な申請書の中から、まずは簡素な申請手続について電子申請導入の可能性を検討していく。
◎未就園児の支援
課題
保育園にも幼稚園にも通っていない、いわゆる「未就園児」は、全国で約182万人いる。
・就園児の保護者のうち子育てで孤独を感じると答えた人が43.8%に上り、これは保育園や幼稚園に通っている保護者よりも10%高いことが判明した。
・一方、北里大学医学部の調査では、未就園児は低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や発達や健康の問題を抱えた子どもで多い傾向。
課題解決に向けた質問・提案
・未就園児が問題なのは、本来、これらの最もセーフティーネットを必要とする子どもたちが保育園や幼稚園というセーフティーネットから漏れてしまっていること。
・また、制度的にも保育園や幼稚園に子どもを通わせることは義務ではなく、現行制度では通わせない自由もあるためになかなか行政の支援が届かないという現状があります。
①現在区では、未就園児に対するどのような支援を実施しているか?
②また、政府は来年度予算に関連費用を計上するとのことですが、来年度に向けて区はどのような施策を検討しているか?
成果
①
区における未就園児支援として在宅子育て支援を実施している。区内に42か所あるおでかけひろばでは、0歳児からご利用いただいており、スタッフが子育てに関する様々な相談を受けたり、利用者同士で情報共有するなど、相談・交流の場と機会を提供することで孤立の防止を図っている。
②
・令和7年度からの「世田谷区子ども計画(第3期)」に向けた令和5年度、6年度を期間とする「子ども・子育て支援事業計画調整計画」を策定している。
・調整計画の重点政策において身近なところで地域の人々や子育て支援につながる場づくりを進めていく予定。
・具体的には、ベビーカーや子どもが歩いて15分程度で行ける身近な場所におでかけひろばを整備していく想定。
・おでかけひろばに日帰り型のレスパイト機能を整備し、安心して子育てができるよう妊娠期を含めた産前産後の支援を充実していく。
◎区立保育園における午睡チェックのICT化について
課題
全国の保育園では、過去に午睡中に園児がなくなってしまうケースがたびたび起きている。
課題解決に向けた質問・提案
原因としてうつぶせ寝による窒息死が考えられることから、東京都の指導監督基準で、「乳児を寝かせる場合は仰向けにすること」と規定し、さらに0歳児は5分に1回、1~2歳児は10分に1回、一人ひとりをチェックし、その都度記録することが行動指針として示されている。
一方、現場の保育士の負担が多大なものとなっている現実あり。
そこで、保育士の方の負担軽減のため、午睡事故防止システムが有効。
私立保育園ではすでに導入いるが、区立保育園では導入されていない。
午睡事故防止システムはたとえば、園児がうつぶせ寝になるとアラートで知らせたり、呼吸や心拍数・体温を計測したり、それらのデータをプリントアウトして監査時の提出資料とすることもできる。
世田谷区では、私立の三茶こだま保育園がすでに導入しており、「システムを入れてからは、身体の向きまでデータ化されるので、保育士のかなりの負担軽減と安心感につながった」ということ。
午睡事故防止システムを導入することで、保育士の方の負担軽減につながり、しいては子どもの事故防止につながると考える。
区立保育園に午睡を導入していただきたいと考える。
また午睡事故防止システムも含め保育園へのICTが必要。
成果
・午睡事故防止システムは、平成29年度から、私立保育園へベビーセンサー等の機器を導入している。
・一方、区立保育園は、公立園が補助対象外となっているため、導入しておらず、目視で午睡チェックを行っている。
・区立保育園に関して、現在、情報化事業計画に基づき、保育業務の負担軽減を図るために、園児の登園、降園に関する管理、健康管理といった業務などのICT化を推進している。
・今後、午睡事故防止センサーの導入について、午睡事故防止の視点や財源の確保等も含め検討していく。
◎保育園の入園状況の情報公開
課題
以前に一次選考にもれたお母様から、「一次選考の結果通知が来たが、区のホームページには何も発表されていない。また、どのような選考方法で結果として何人が入園できたのか、自分はどのくらいの位置にいるのか、何が原因なのか、点数は何点か、もう少し情報が欲しい。」というご意見をいただいた。
課題解決に向けた質問・提案1
より詳細な情報提供すべき、ホームページでも提供すべき、と前回質問したが、その後どうなったのか?
成果
ホームページに新たなページを作成し、「入園申込み」「書類の書き方」「保育料」「支給認定」などに関する質問を掲載し、情報提供した。
さらに、初めて保育園を申込む保護者を対象に説明会を開催。
来年10月に幼児教育・保育の無償化に実施に向け、さらに情報提供していく。
課題解決に向けた質問・提案2
ホームページのトップページから入ると、認可保育園の空き情報が園ごとに閲覧する方式に変わっていて、一覧性が失われている。まだ一覧ページにたどり着けない、空き情報をわかりやすく情報提供するために工夫していただきたい。前回も質問したが、どうなったのか?
成果
地域ごとに一覧で確認できるよう、改善した。
議会中継動画
定例会名
- 令和5年第2回定例会 一般質問
- 令和5年第1回定例会 予算委員会
- 令和5年第1回定例会 一般質問
- 令和4年第4回定例会 一般質問
- 令和4年第3回定例会 決算委員会
- 令和4年第3回定例会 一般質問
- 令和4年第2回定例会 一般質問
- 令和4年第1回定例会 予算委員会
- 令和4年第1回定例会 一般質問
- 令和3年第4回定例会 一般質問
- 令和3年第3回定例会 決算委員会
- 令和3年第3回定例会 一般質問
- 令和3年第2回定例会 一般質問
- 令和3年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第4回定例会 一般質問
- 令和2年第3回定例会 決算委員会
- 令和2年第3回定例会 一般質問
- 令和2年第2回定例会 一般質問
- 令和2年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第1回定例会 一般質問
- 令和元年第4回定例会 一般質問
- 令和元年第3回定例会 決算委員会
- 令和元年第2回定例会 一般質問
- 平成31年第1回定例会 予算委員会
- 平成31年第1回定例会 一般質問
- 平成30年第4回定例会 一般質問
- 平成30年第3回定例会 決算委員会
- 平成30年第3回定例会 一般質問
- 平成30年第2回定例会 一般質問
- 平成30年第1回定例会 予算委員会
- 平成30年第1回定例会 一般質問
- 平成29年第4回定例会 一般質問
- 平成29年第3回定例会 決算委員会
- 平成29年第3回定例会 一般質問
- 平成29年第2回定例会 一般質問
- 平成29年第1回定例会 予算委員会
- 平成29年第1回定例会 一般質問
- 平成28年第4回定例会 一般質問
- 平成28年第3回定例会 決算委員会
- 平成28年第3回定例会 一般質問
- 平成28年第2回定例会 一般質問
- 平成28年第1回定例会 予算委員会
- 平成28年第1回定例会 一般質問
- 平成27年第4回定例会 一般質問
- 平成27年第3回定例会 決算委員会
- 平成27年第3回定例会 一般質問
- 平成27年第2回定例会 一般質問
- 平成27年第1回定例会 予算委員会
- 平成27年第1回定例会 一般質問
- 平成26年第4回定例会 一般質問
- 平成26年第3回定例会 決算委員会
- 平成26年第3回定例会 一般質問
- 平成26年第2回定例会 一般質問
- 平成26年第1回定例会 予算委員会
- 平成26年第1回定例会 一般質問
- 平成25年第4回定例会 一般質問
- 平成25年第3回定例会 決算委員会
- 平成25年第3回定例会 一般質問
- 平成25年第2回定例会 一般質問
- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会
- 平成25年第1回定例会 一般質問
- 平成24年第4回定例会 一般質問
- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会
- 平成24年第2回定例会 一般質問
- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会



