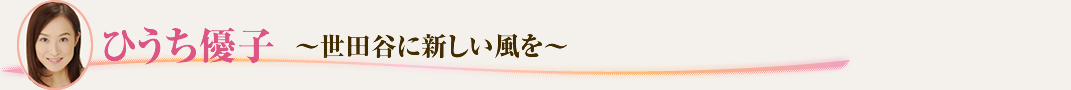
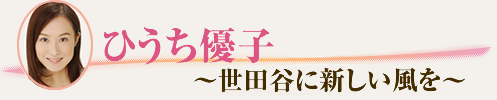
【安心・安全】記事一覧
世田谷消防団始式


今日は、毎年参加している、世田谷消防団始式に出席。
ここ最近、新年会続きで、早くも体調を崩してしまいましたが、なんとか復活一歩手前……
体調管理には、誰よりも気を付けていたのですが、それでも身体は正直だなと実感。疲れのサインかな?
消防団との縁は深く、私は、消防団運営委員であります。
消防団とは、本業を持ちながらも、地域のために消防活動に携わっている方で、常勤の消防員とは別の組織です。
活動は、消火のみならず、スタンドパイプ訓練、地域のパトロール、震災時の避難誘導、など、多岐にわたっております。
消防団の方の活動は、頭が下がる想いです。いつもありがとうございます。
令和6年予算委員会が終わりました その2

【予算委員会その2】
予算委員会の質問の続きです。
福祉保健委員会所管
●双子支援について〜第3子出産費助成〜→実現!
●ツインズプラスサポート支援
●保険証の廃止について
都市整備委員会所管
●世田谷区のコミュニティサイクルについて
●自転車ヘルメット購入助成について→実現!
●交通違反自転車への青切符制度の導入について
文教委員会所管
●学校での自転車ヘルメット着用の周知について
●標識教育について→実現!
●奥沢駅への図書の宅配ボックス、ブックボックスの整備
●プログラミング教育の人材育成
補充質疑
●区営団地へのエレベーター設置について
●民有地の倒壊寸前の木と塀について
●学校への防災ヘルメットの配備について
令和6年第1回定例会 予算委員会が終わりました〜その1〜

【予算委員会その1】
令和6年 第1回定例会 予算委員会が終わりました。
今回も、7つの委員会の所管で質問いたしました。
総括質疑
企画総務委員会所管
区民生活委員会所管
福祉保健委員会所管
都市整備委員会所管
文教委員会所管
補充質疑
とりあげたテーマは下記の通り。2回に分けて投稿します!
総括質疑
●自転車の車道通行の逆走対策
道路の右側に「自転車は車道の左側通行」のサイニングをする
→実現!
●図書の宅配ボックス、ブックボックスの整備→実現!
●予約本の待ち状況の通知
企画総務委員会所管
●災害時の要支援者の避難について
●新リース会計基準について
区民生活委員会所管
●相続登記の義務化の周知
●戸籍・住民票などの郵送請求のオンライン決済について
●世田谷清掃工場の建て替えに伴うCO2対策について
続く
◎三軒茶屋キャロットタワー前の信号機のない横断歩道への信号機設置について
課題
・以前から次のような声をいただいている。
「三軒茶屋キャロットタワー前、都道の世田谷通りと三軒茶屋の喫煙所の間の横断歩道に信号機を設置してほしい。車で渋谷方面から右折をするときになかなか曲がれない、歩行者の安全のためにも信号機を設置してほしい」
課題解決に向けた質問・提案
世田谷通りと目青通りが交差する箇所は右折や左折してくる車も多く、横断歩道を通行する歩行者にとっても危険。歩行者の安全確保のためにも、車両のためにも、新たな信号機の設置が必要と考えるが、見解を伺う。
成果
・委員お話しの横断歩道は、都道の世田谷通り内に位置し、お話しのとおり世田谷通りから右折、左折する車両が一方通行の規制となっている目青通りに向かって通行している。
・歩行者用信号機は設置されていないが、キャロットタワー周辺は市街地再開発事業に伴い整備され、その際、周辺の交通環境につきましても交通管理者である警察と十分な協議を経て現在の状況に至ったものと認識している。
・信号機を新設するには幾つかの条件を満たす必要があるが、現場確認を行った上で警察へ申し伝える。
◎電動キックボードの新ルール適用
課題
・令和2年9月の決算委員会で初めて取り上げ、その後も何度か質問した。
・電動キックボードは、手軽に乗れることから交通ルール違反が後を絶たず、2020年から2022年11月の3年間に全国で起きた電動キックボードによる人身事故のうち、東京が6割の46件で最多となり、死亡事故も起きている。
課題解決に向けた質問・提案
・令和4年4月に道路交通法が改正され、電動キックボードの交通ルールも大幅に改正された。
・新ルールが適用されると、最高速度6km以下で走行する場合は運転免許が不要で、ヘルメットは努力義務となる。
・ただし、16歳未満は運転できない、信号無視などの一定の違反を3年以内に2回以上繰り返すと講習が義務づけられるなど、自転車とは違ったルールも適用される。
・現行のルールでさえよく理解しないで右側通行や歩道を走行しての事故が発生している中で、新ルールが適用されると、全て電動キックボードが歩道で通行できると勘違いするなど、さらなる事故が増えることが心配。
・そこで、世田谷区交通安全計画において電動キックボードを位置づけるとともに、新ルールを警視庁と協働で区民に啓発する必要があると考える。見解を伺う。
成果
・世田谷区及び警察署、消防署、交通事業者など関係機関と連携して、世田谷区交通安全計画を作成し、総合的な交通安全対策に取り組んでいる。
・この計画では、電動キックボードについて、区と警察署においては実証実験や法改正の動向に注視するとともに、運転者に対して法令遵守の徹底などの啓発を行うと位置づけている。
・今年7月に施行されます電動キックボードの新ルールは、これまで複雑だったLUUPなどシェアリングサービスの車両と、条件を満たす個人所有の車両の異なるルールが統一され、分かりやすくなる一方、16歳以上は無免許でも運転でき、時速6キロ以下であれば歩行者を優先した上で歩道を走行できるようになるなど、混乱が予想されている。
・区は、警察署と連携、協働し、広報誌への掲載や掲示板へのポスター掲示など、電動キックボードの交通ルールの普及啓発に努めていく。
◎公園への防犯カメラ設置について
実現!
課題
・令和元年に、質問した。
・「治安上、公園内に防犯カメラを設置してほしい。」との声がある。
・上用賀公園を管轄する町会の方から、次のご意見がある。
「防犯カメラの要望、上用賀公園に防犯カメラを設置したいが、区に聞いたところ、公園は東京都の決まりで防犯カメラ設置助成が出ない、全て町会で負担しなければならない。防犯上、世田谷区が防犯カメラを設置してほしい。」
課題解決に向けた質問・提案1
・行政として設置できないのであれば、事業者による設置があり、自動販売機事業者による防犯カメラ整備が有効。この手法は、公園内に自動販売機を設置する条件で、その利益の一部を防犯カメラ設置に充てるというもので、進めていただきたい。
・上用賀公園への防犯カメラ設置の進捗状況について伺う。
成果
・現在、区立公園への防犯カメラの設置は、委員お話しのとおり、公園内に自動販売機を設置する事業者との連携事業により順次増設を進めている。
・上用賀公園も、設置の検討を継続しているが、庁内関係所管、管轄警察署と必要性、有効性を検証した結果、他公園への設置を優先し、いまだ同公園への防犯カメラ設置には至っていない。
・しかし、前回委員から御質問いただいた後、令和元年度末には、地元町会が都及び区の補助事業を活用して、街頭防犯カメラを周辺に6か所増設した。他町会、商店街の御協力もあり、現在、同公園周辺半径1キロ範囲内で計67か所に街頭防犯カメラが設置されるなど、治安対策の充実を図っている。
課題解決に向けた質問・提案2
何より公園こそ安全上の観点から、防犯対策として、行政として公園内に防犯カメラを設置すべきと考える。公園内への防犯カメラ設置について、見解を伺う。
成果
・区立公園内への防犯カメラ設置は防犯上大変有効であると認識している。
・事業者との連携事業により、現在、区内11公園、21台の防犯カメラを設置、運用中であり、本年度末にはさらに4公園、4カメラの増設を予定している。
・また、各種事業者への働きかけを強化し、一部事業者から同種カメラ設置事業に賛同の意向をいただくなど、今後も設置機器の確保と、さらなる設置促進に努める。
◎オリンピック・パラリンピックの食品衛生監視について
課題
この夏、オリンピック・パラリンピック東京2020大会が、コロナウイルスの影響で無観客開催された。
・世田谷区でも、無観客で馬術競技が開催されたが、選手、スタッフ、VIPなどの方々は来日しており、地元自治体としてしっかりとおもてなしを行い、対応する必要があった。コロナ禍、大変だった。
課題解決に向けた質問・提案1
区内で唯一開催された馬術の舞台、馬事公苑では、保健所の食品衛生監視の職員の方が毎日通って、選手やスタッフの食の健康を守ったとのこと。具体的にどのような活動をされていたのか、伺う。
成果
・7月23日から9月5日まで開催されたオリンピック・パラリンピックでは、提供する食品の安全確保の観点から、選手、厩務員、報道関係者、運営スタッフ等を対象とした飲食提供施設の食品衛生監視を行った。
・大会に前後して厩務員宿泊施設が開設されており、46日間で延べ166名が衛生監視に従事している。
・新型コロナウイルス感染拡大期にもかかわらず、杉並保健所及び中野保健所からも延べ33名の応援協力を受け、3区の協力体制の下で監視業務を行った。
・具体的な対応としては、保健所の食品衛生監視員が2人1組で、1日2回飲食提供施設の厨房等に立ち入り、厚生労働省作成の大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいて、加熱温度が適正か、調理品の衛生管理が適正かなど食品取扱状況などを確認するとともに、細菌検査、アレルゲン検査などの食品検査、職員従事者の手指や調理器具等の拭き取り検査を実施いたしました。検査結果等は良好で、選手等からの苦情もなく、大会は無事終了した。
課題解決に向けた質問・提案2
・無観客で開催された馬術競技でも、コロナ対策で忙しい中、保健所の職員の方が活躍されていたことを改めて知り、保健所が新型コロナウイルスだけではなく、食品衛生の面でも大会を支えていたこと、大変頭が下がる。
・長期間の監視活動で様々な貴重な経験を積んできたと考える。この経験を、世田谷区だけではなく、オリンピック・パラリンピックを開催していない自治体とも共有し、今後の大規模イベントの開催のときの財産として活用していくべきと考える。
・特にホスト側として、食品衛生監視は外交、国防にも関わる大変重要なことであります。保健所はこの経験をどのように生かしていくのか伺う。
成果
・世田谷保健所では、令和元年度のラグビーワールドカップ開催に伴い、会場である調布市の調理施設等に食品衛生監視員を派遣した。その経験を生かして、今大会の監視手法や監視スケジュールを作成した。
・同じく、令和元年度に馬事公苑で開催したオリンピックテスト大会での弁当保管温度の検証実験を含めて、世田谷保健所が行った監視活動内容は全て記録している。
・今後、本大会の衛生監視における課題を抽出した上で、東京都が開催している東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の監視指導に関する検討会で最終報告を行うなど、大会運営上の情報を他保健所等と共有するとともに、同様の大規模イベント等が開催された際に、今回の経験が十分に生かせるよう、実際に行った業務の詳細や今後の課題を保健所内でしっかり伝承していく。
・また、今大会で衛生監視業務において近隣区からの応援協力を初めて得た。
・大規模食中毒発生時や災害時など、他自治体との相互連携が必要となった場合に迅速かつ的確に対応ができるよう、全ての業務を振り返り、危機管理対策にも反映して、食の安全安心の確保に取り組んでいく。
◎大井町線の開かずの踏切解消について
課題
東急大井町線には多数の踏切が残存している。
課題解決に向けた質問・提案1
・通勤通学の安全性、利便性の観点からも、踏切解消の早急な対策が必要。
・2010年以降、自由が丘~上野毛間だけで10件もの事故が発生している。
・目黒区では、今年度予算に自由が丘駅周辺地区のまちづくり活動の支援と鉄道立体化の検討について予算計上しているが、目黒区との関わりと連携はしているか?伺う。
成果
東京都が平成16年6月に策定した踏切対策基本方針では、自由が丘駅付近の東横線と緑が丘駅付近〜等々力駅付近までの大井町線が併せて、鉄道立体化の検討対象区間として位置づけられている。
・そのため、目黒区が実施している調査検討に世田谷区も参加してお李、今後も引き続き目黒区と連携して検討を進めていく。
課題解決に向けた質問・提案2
目黒区の動きに合わせて、世田谷区内にある大井町線の自由が丘駅~等々力駅付近の開かずの踏切解消を図るべきだと考える。見解を伺う。
成果
・道路と鉄道の立体化には多くの費用と期間を要し、さらには、交差する都市計画道路の整備や地域におけるまちづくりなどについても検討する必要がある。
・立体化に取り組むべき路線として、引き続き東京都や目黒区及び鉄道事業者などと連携を図りながら、開かずの踏切解消に向けて取り組んでいく。
◎三宿通り及び世田谷公園周辺の生活道路の安全対策について
実現!
課題
・三宿周辺のまちづくりとして、特に子どもが多いエリアでは安全対策が最重要課題。
・例えば、池尻保育園の前の交差点の保育園側には、ガードレール以外、ボラードなどの整備は何もない。
課題解決に向けた質問・提案
・対策として、歩道に沿った信号待機スペースの確保、そのために段差をなくしてガードレールの歩道の線にボラードをつける。また、現在のボラードは進入禁止用であって対車両用ではないが、対車両衝突用の強度の高いボラードを設置するなど、工夫した安全対策が必要と考える。見解を伺う。
・また、そのほかにも、平安幼稚園、池尻小学校周辺、246三宿の交差点の信号機の青の時間を延長することなど、三宿周辺一帯の通学路の安全対策が求めらる。併せて伺う。
成果
1点目、池尻保育園の前の交差点については、再度現地を確認した上で、必要な安全対策を検討する。
2点目。国道246号三宿交差点の信号機等々の時間の延長については、関係所管とも連携して、警察のほうへ申入れをしたい。
◎駅のホームドア・エレベーター整備について
実現!
課題
・区民の方から、世田谷区の各駅にホームドアとエレベーターを整備してほしい、との声がある。
・特にエレベーターは、三軒茶屋南口へのエレベータ設置の声が多い。
課題解決に向けた質問・提案1
・2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催において公共交通機関の安全性、快適さが求められ、駅施設の整備が特に大切と考える。また、バリアフリーの観点からも、駅のホームドア・エレベーター設置は必須。
・世田谷区には41の駅があるが、以前からホームドア、エレベーターを整備してほしいとの声がある。
・その後、ホームドアに関しては、三軒茶屋駅を初め、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅など着実に進んでおり、またエレベーターは、三軒茶屋駅南側に待望のエレベーターが整備された。
・最終的には全ての鉄道駅にホームドア、エレベーターを整備していただきたい。現時点での設置状況と今後の整備計画について伺う。
答弁
・昨年の6月以降のホームドアの整備状況は、田園都市線の桜新町駅、池尻大橋駅、大井町線の九品仏駅、二子玉川駅においてホームドアの使用を開始している。等々力駅は今年度中の使用開始を予定している。
・小田急電鉄は、下北沢駅地下1階ホーム、東北沢駅、世田谷代田駅において使用を開始している。梅ヶ丘駅は本年度中の使用開始を予定している。
・エレベーターの整備は、田園都市線の三軒茶屋駅南口で使用を開始しており、桜新町駅南口は、令和2年度の使用開始を予定している。
課題解決に向けた質問・提案2
・前回の質問では、京王井の頭線の下北沢駅について、以前からエレベーターを設置してほしいとの声を取り上げた。特に西口側はバリアフリー対応が遅れており、エレベーター設置、ホームドア設置、そしてトイレも老朽化しており、バリアフリー対応のトイレ整備が必要と考える。
・既存の西口改札口のバリアフリー対応について、今後の予定を伺う。
成果
・井の頭線下北沢駅は、本年3月までに小田急線の連続立体交差事業などの影響範囲となる渋谷側の駅舎が完成し、改札階からホーム階へのエレベーター、エスカレーター及びトイレの整備が完了している。
・西口改札口のバリアフリー化については、現時点では整備内容及び整備時期は公表されていないが、現在、大規模な改修工事が進められており、早期にバリアフリー化が図られるよう、引き続き働きかけていく。
課題解決に向けた質問・提案3
・バリアフリーの観点から、ホームドア・エレベーター工事への行政の助成を行っている。
・ホームドアは1日当たりの平均利用者数が10万人以上の駅において、都の補助対象事業の場合には、補助対象事業費の3分の1かつホームドア1列につき6000万円を上限に、都の補助対象事業でない場合には、補助対象事業費の6分の1かつホームドア1列につき3000万円を上限に世田谷区が助成を行う。
・エレベーターに関して、1日当たりの平均利用者数が1万人以上の駅において、補助対象事業費の3分の1かつ7000万円を上限に助成することになっている。この点、各電鉄の事業に対してどこまで助成をするかも考える必要があると思うが、区民の方の利便性、安全性を確保すべきと考える。
・現在、小田急線では、ホームドアの設置が進められているが、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見駅についてはホームドアの整備計画がない状況。
・豪徳寺以西へのホームドアも設置していただきたい。見解を伺う。
成果
・現在、小田急電鉄は、代々木八幡駅から梅ヶ丘駅までの6駅において、2020年度までの使用開始を目標に、ホームドアの設置を進めている。
・また、その後、国土交通省が示した整備方針に基づき、一日の利用者数が10万人以上の町田駅、登戸駅など、区外にある八駅を優先してホームドアの設置を進めていくこととしている。
・一方、東京都は先月、鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方を示し、この考え方に基づき、優先的に整備をする駅に対する補助の拡大充実を図り、鉄道バリアフリーの取り組みを強力に推し進めていくとしている。
・ホームドアの整備に関して、ユニバーサルデザインの観点から非常に重要だと認識しており、引き続き、東京都及び鉄道事業者の動向を注視していく。
議会中継動画
定例会名
- 令和5年第2回定例会 一般質問
- 令和5年第1回定例会 予算委員会
- 令和5年第1回定例会 一般質問
- 令和4年第4回定例会 一般質問
- 令和4年第3回定例会 決算委員会
- 令和4年第3回定例会 一般質問
- 令和4年第2回定例会 一般質問
- 令和4年第1回定例会 予算委員会
- 令和4年第1回定例会 一般質問
- 令和3年第4回定例会 一般質問
- 令和3年第3回定例会 決算委員会
- 令和3年第3回定例会 一般質問
- 令和3年第2回定例会 一般質問
- 令和3年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第4回定例会 一般質問
- 令和2年第3回定例会 決算委員会
- 令和2年第3回定例会 一般質問
- 令和2年第2回定例会 一般質問
- 令和2年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第1回定例会 一般質問
- 令和元年第4回定例会 一般質問
- 令和元年第3回定例会 決算委員会
- 令和元年第2回定例会 一般質問
- 平成31年第1回定例会 予算委員会
- 平成31年第1回定例会 一般質問
- 平成30年第4回定例会 一般質問
- 平成30年第3回定例会 決算委員会
- 平成30年第3回定例会 一般質問
- 平成30年第2回定例会 一般質問
- 平成30年第1回定例会 予算委員会
- 平成30年第1回定例会 一般質問
- 平成29年第4回定例会 一般質問
- 平成29年第3回定例会 決算委員会
- 平成29年第3回定例会 一般質問
- 平成29年第2回定例会 一般質問
- 平成29年第1回定例会 予算委員会
- 平成29年第1回定例会 一般質問
- 平成28年第4回定例会 一般質問
- 平成28年第3回定例会 決算委員会
- 平成28年第3回定例会 一般質問
- 平成28年第2回定例会 一般質問
- 平成28年第1回定例会 予算委員会
- 平成28年第1回定例会 一般質問
- 平成27年第4回定例会 一般質問
- 平成27年第3回定例会 決算委員会
- 平成27年第3回定例会 一般質問
- 平成27年第2回定例会 一般質問
- 平成27年第1回定例会 予算委員会
- 平成27年第1回定例会 一般質問
- 平成26年第4回定例会 一般質問
- 平成26年第3回定例会 決算委員会
- 平成26年第3回定例会 一般質問
- 平成26年第2回定例会 一般質問
- 平成26年第1回定例会 予算委員会
- 平成26年第1回定例会 一般質問
- 平成25年第4回定例会 一般質問
- 平成25年第3回定例会 決算委員会
- 平成25年第3回定例会 一般質問
- 平成25年第2回定例会 一般質問
- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会
- 平成25年第1回定例会 一般質問
- 平成24年第4回定例会 一般質問
- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会
- 平成24年第2回定例会 一般質問
- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会


