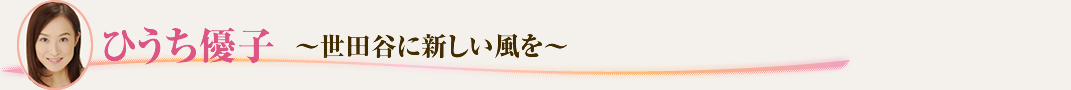
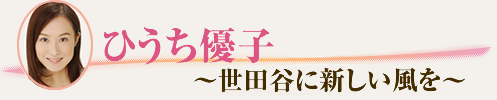
【教育】記事一覧
【令和7年 第3回定例会 決算委員会6】
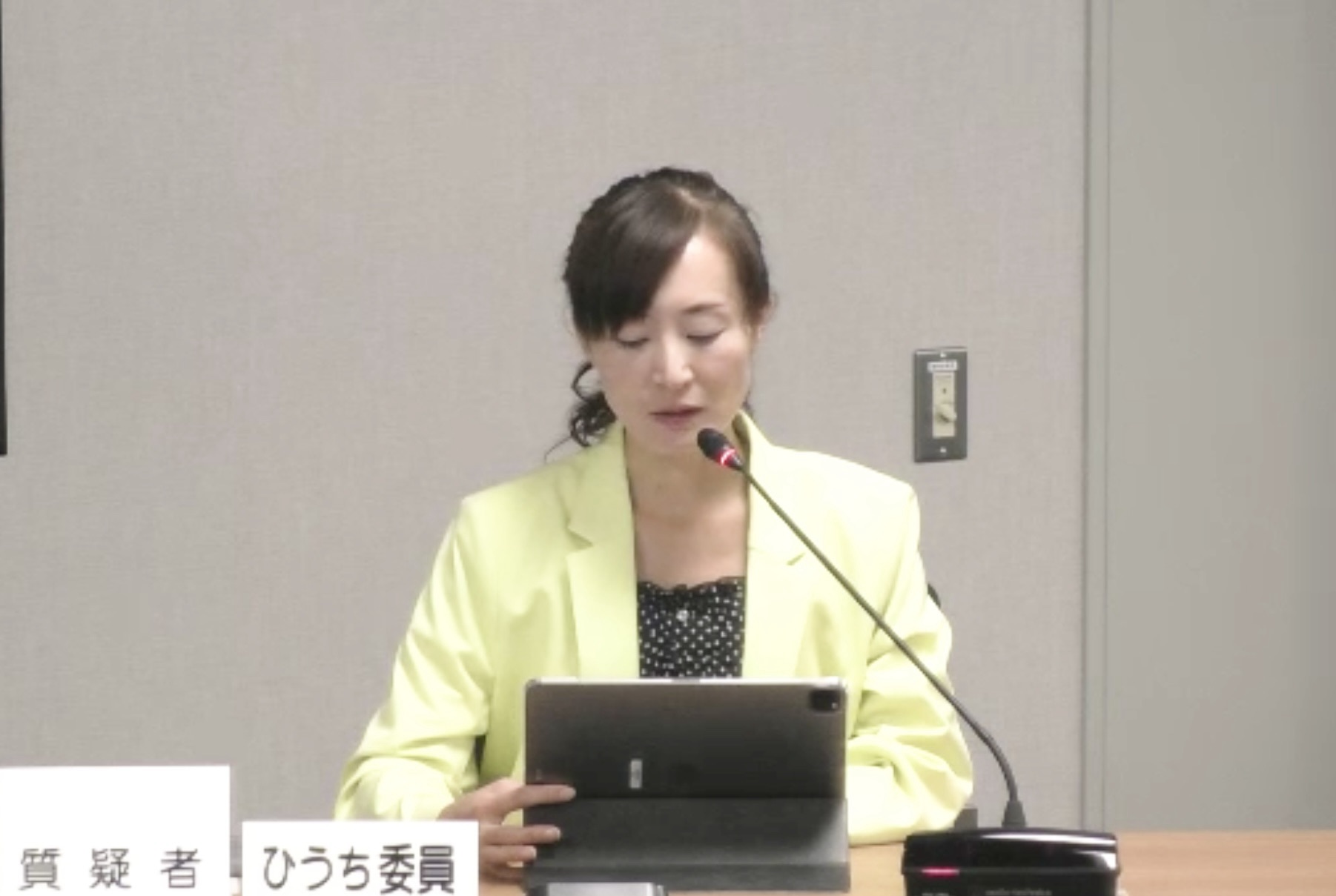
文教委員会所管での質問は、4テーマ。
● キャリア教育の全区展開
●図書館のWi-Fiの繋がりにくさの改善
●子ども達のダンス・音楽の発表の場の提供
● 全国学力・学習状況調査の結果について
この中で、図書館のWi-Fiの繋がりにくさの改善は、実現予定!
「来年度には、区立図書館で機器の更新や通信回線の高速化を実施する。」とのことです。
キャリア教育も、実現予定!
「キャリア教育の好事例を、学校支援コーディネーター同士の情報共有により、各校のニーズに応じて展開する。」
との答弁!
順調です。
行政視察④ 【Town &Gown構想による新たな街づくり@東広島市】


行政視察4箇所目。東広島市の「Town &Gown構想」による新たな街づくり
・東広島市は、広島大学が在る所。
・市と大学の教育・研究資源を融合しながら、科学技術イノベーションを活かして、地方創生に貢献。学園都市として、大学生との連携を行っている。
・commonプロジェクトを実施。commonプロジェクトとは、市と大学が組織同士で、市だけでは解決できなあ困難な地域課題を、大学の知的・人的資源を活用し、研究・先端技術を用いて解決に結びつけ、世界に貢献するイノベーションを目指す。
・事例
小規模校では、生徒数の減少により、子ども同士が協働で学ぶことが困難になり、対話や議論を通じて、個人や集団としての意見を形成したり、多人数を相手に発表する場所が少なくなっている。そこで、広域交流型オンライン学習を、東広島市と広島大学で共同で行なっている。
遠隔授業(離れた教室の意見を自動で収集・分類する)のAI学習支援技術の開発を大学が中心となって実施。
大学・行政・企業の連携により、大きな成果を生む成功事例。世田谷区も、区内に17の大学があります。もっと大学と連携して、様々な政策を、アイディアを出し合って協働して進める必要だと実感しました。
令和6年 一般質問が終了しました!〜二子玉川の堤防整備が実現!〜一歩一歩前進しています

今回も、一般質問をいたしました!
テーマは下記の通り。
●「小1の壁」対策
●チーム担任制を導入しよう!
●区役所窓口に、生成AIを活用しよう!
●二子玉川の無堤防地域への堤防整備が実現!
●豪雨対策〜河川の内水氾濫を防ぐために、樋門へのポンプ設置、流向計の設置が必要〜
●豪雨対策〜下水菅の分流式地域の雨水菅の整備を〜現在3割。残り7割の整備を!
●豪雨対策〜ピークカットのために、調節池の整備を!〜
●豪雨対策〜豪雨対策基本方針で、目標降雨プラス10ミリに引き上げを!〜
●世田谷区のレンタサイクルから民間シェアサイクルの移行を丁寧に対応すべき。
令和7年 予算委員会 総括質疑
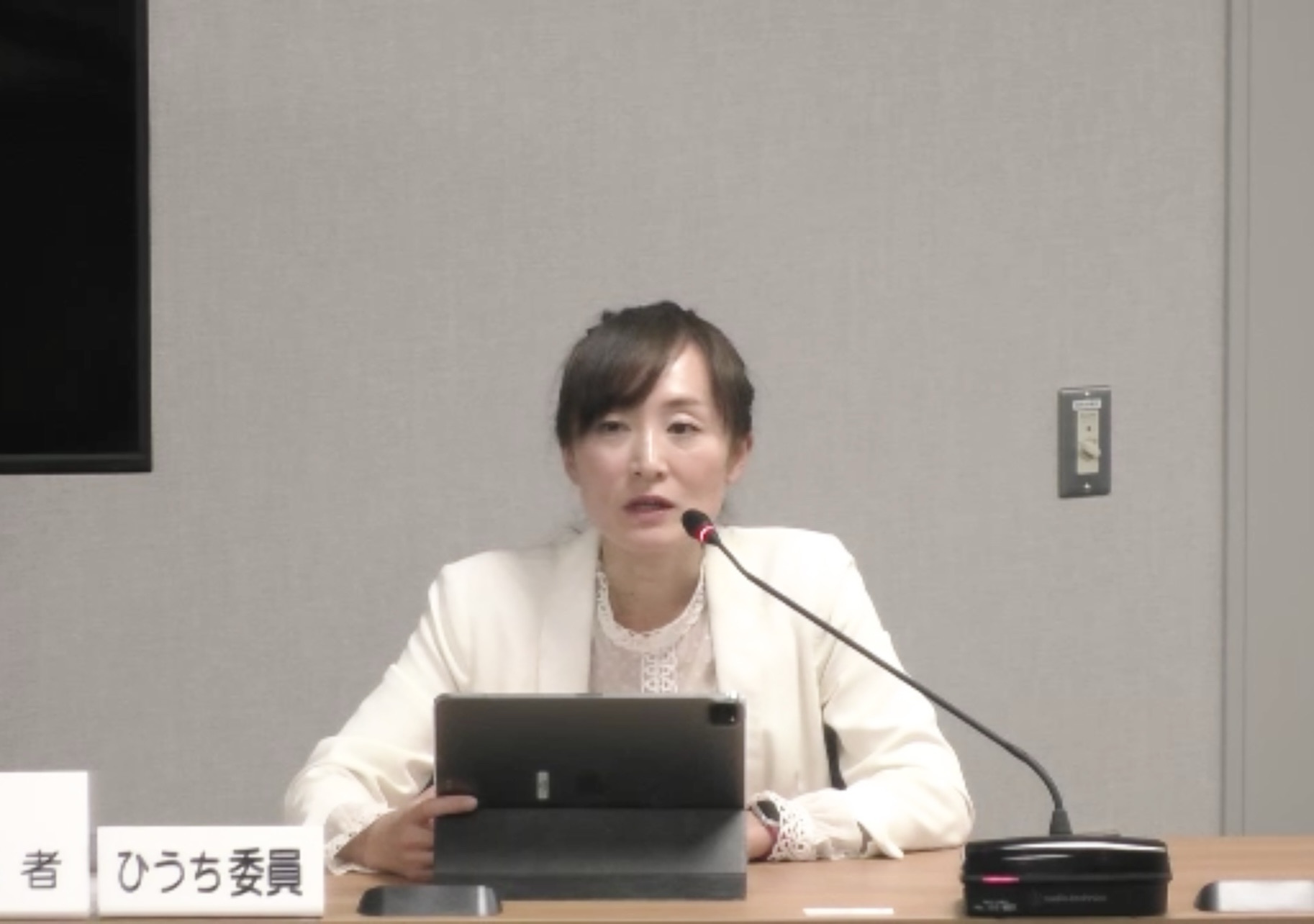
総括質疑では、2テーマ
⚫︎小中学生への自転車の標識教育
⚫︎東京都ベビーシッター事業への参入
簡潔にまとめます。
総括質疑
⚫︎小中学生への自転車の標識教育
質問
自転車は軽車両。標識が適用される。しかし、車の運転免許を持っていない小中学生は標識を学ぶ機会がない。
例えば、
・道徳の授業やホームルームの時間等を活用しての周知徹底
・学校の廊下への標識の掲示
・区立中学校の生徒手帳への標識の記載
・学級通信における標識クイズの実施など実施すべき。
→実現!
・小1、中1で標識のクリアファイルを配布済。
・長期休業日前の生活指導の内容に、ヘルメット着用と合わせて道路標識の指導も含めていく。
・ 廊下への標識の掲示を検討する。
⚫︎東京都ベビーシッター利用支援事業への参入
質問
・「東京都負担100%の東京都ベビーシッター利用支援事業」を世田谷区でも導入すべき。
・この制度は,東京都の認定事業者において,無料でベビーシッターを利用することができる制度。利用できる時間数の上限はあるものの、「保育認定」が不要で事前の区市への手続きも必要もない。
・23区中、19区が導入。
・導入済みの港区では、人気の施策である故に、都負担利用条件に加え、区独自で対象児童の年齢を5歳から小学6年生まで引き上げ、且つ、来年度は区の予算で追加助成の予定。
→答弁
・世田谷区で過去に密室における預かりで刑事事件に至った事故を経験し、またこの間認可外保育施設での重大事故等が度重なり、保育の質の確保には不断の努力が必要。現時点で事業実施は難しい。
・全国保育サービス協会や東京都、各事業者とも意見交換等を行いながら、「保育の質の確保」を果たす方策について、当面の課題として研究する。
令和6年予算委員会が終わりました その2

【予算委員会その2】
予算委員会の質問の続きです。
福祉保健委員会所管
●双子支援について〜第3子出産費助成〜→実現!
●ツインズプラスサポート支援
●保険証の廃止について
都市整備委員会所管
●世田谷区のコミュニティサイクルについて
●自転車ヘルメット購入助成について→実現!
●交通違反自転車への青切符制度の導入について
文教委員会所管
●学校での自転車ヘルメット着用の周知について
●標識教育について→実現!
●奥沢駅への図書の宅配ボックス、ブックボックスの整備
●プログラミング教育の人材育成
補充質疑
●区営団地へのエレベーター設置について
●民有地の倒壊寸前の木と塀について
●学校への防災ヘルメットの配備について
令和6年第1回定例会 予算委員会が終わりました〜その1〜

【予算委員会その1】
令和6年 第1回定例会 予算委員会が終わりました。
今回も、7つの委員会の所管で質問いたしました。
総括質疑
企画総務委員会所管
区民生活委員会所管
福祉保健委員会所管
都市整備委員会所管
文教委員会所管
補充質疑
とりあげたテーマは下記の通り。2回に分けて投稿します!
総括質疑
●自転車の車道通行の逆走対策
道路の右側に「自転車は車道の左側通行」のサイニングをする
→実現!
●図書の宅配ボックス、ブックボックスの整備→実現!
●予約本の待ち状況の通知
企画総務委員会所管
●災害時の要支援者の避難について
●新リース会計基準について
区民生活委員会所管
●相続登記の義務化の周知
●戸籍・住民票などの郵送請求のオンライン決済について
●世田谷清掃工場の建て替えに伴うCO2対策について
続く
◎キャリア教育について
実現!進行中
課題
小中学校教育の中に、社会人経験した人材が少ない。
課題解決に向けた質問・提案
・社会人経験をした人材を教育に生かすことが必要であり、様々な職種に携わっている人材を教育の中に入れることで、いろいろな大人を見て育つことができ、教育の観点から重要である。
・例えば、法律、金融、経済、メディア、ITといったそれぞれの専門分野の方を教育現場に入れることで、経験豊かな方々の考え、仕事の内容を学ぶことができ、刺激的で子どもたちによい影響を与えると考える。また、選択肢が増える。
・そして、一つの職を全うされている方、転職をされている方、パラレルワークをされている方など、様々な職業人の話を聞くことで、職業は一つではない、人生はやり直しが利くんだといったメッセージを伝えることもできる。
・また、特に学校の保護者の方には様々な職業の方がいるので、キャリア教育としてよい環境にあり、今後、積極的にその学校の保護者の方々によるキャリア教育の場をつくることも効果的と考える。
・進捗状況と今後について伺う。
成果
・教育委員会では、今年度、これまでのキャリア教育の推進と発展に資する功績が認められ、キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣賞を受賞した。
・現在各学校では、地域や企業、事業所など、様々な人々との関わりを基盤に、学び豊かなキャリア教育を展開している。
・区内小学校では、青年会議所と連携し、子どもたちが大人とともに地域の防犯につながる学習活動を行い、自分たちの力が社会にいい影響を与えたことを実感できた事例もある。
・教育委員会では、今年度、キャリア教育の充実を図ることを目的に委員会を立ち上げ、実践内容の検討やキャリアパスポートの活用等について検討を重ねてきた。
・今後、これらの内容をリーフレットにまとめ、全校に配付する。加えて、各学校の好事例を掲載したキャリア・未来デザイン教育カタログを新たに発行し、教員はもとより、保護者にも紹介し、キャリア教育の実践を広く紹介していく。
・さらに、新たな取組として、子どもたちが様々な職業の大人の方と体験的に関わることができる子どもハローワークを開始し、キャリア教育の一層の推進を図っていく。
◎教科担任制について
課題
・学級経営、教科、全て1人の教師が担当する現状は、教員の負担が大きい。
・子供にとって、1人の教師から学ぶより、いろいろな教師と接した方が、選択肢が増える。
課題解決に向けた質問・提案
・私自身が小学校から教科担任制で育ったことから、自分自身の経験を踏まえ、学級経営と教科を分離することで教員の負担軽減につながること、また、子どもたちにとって多くの先生に接する機会が増えることなどから、教科担任制を積極的に導入するように今まで何度か質問した。
・令和3年の第4回定例会では、区内の小学校一校が推進校に指定されていることから、この取組や、区や都の動向を踏まえて検討していくとの答弁だった。
・現在、都内では10校で教科担任制を導入しており、様々なメリットが報告されている。
・例えば、これまでは教員の方が朝の打合せ後、教員室を出ると放課後まで出たきりだったが、それも解消されたことで、空いた時間で生徒一人一人の提出物を丁寧に見ることができ、テストの採点の評価のぶれもなくなった。以前は午後九時まで残業するのが当然で、授業がない土曜日も出勤して仕事に追われていたが、今は定時で退勤できるようになり、自分の子どもの子育てや読書などの自己啓発ができるようになった等。
・一方で、教科担任制の課題は、教員の数が足りないと導入できないという点。そこで、世田谷区のモデル校での実績を踏まえた進捗状況と今後について伺う。
成果
・小学校の高学年における教科担任制は、専門性の高い教科指導を実現し、中学校教育への円滑な接続を図ることや、複数の教員が児童と関わることで、多面的、多目的で、よりきめの細かい個に応じた指導を実施することが可能となる。
・これまで世田谷区では、下北沢小学校が都教育委員会の研究指定校として教科担任制の研究を進めており、教員の教科指導力の向上が見られたことや、チームとして生活指導に取り組み、児童理解が進んだことなどの成果があった。
・その成果も踏まえ、区教育委員会では次年度より、現在、専科教員が2名しか配置されていない学校について、区独自の講師を配置できるよう拡充をし、教科担任制の充実を図っていく。
◎プログラミング教育の人材確保について
課題
以前に、プログラミング教育をバックアップする人材を探すのが大変という声をいただいた。
課題解決に向けた質問・提案
・プログラミング教育は各教科の授業の中で計画的に行い、問題の解決に必要な手段があることに気づき、論理的思考力を育むことを狙いとする教育。
・学校におけるプログラミング教育を支援する人材、特にプログラミング教育に精通した人材の確保を行っていただきたい。見解を伺う。
成果
・教育総合センターでは、現在、大学や企業等との連携構築を進めており、その中でICTやプログラミングの指導ができる人材をリスト化していく予定。
・この連携の仕組みの中で、プログラミングの指導をはじめ、学校のニーズに沿った人材を紹介していく。
・ほかにも、センター内では理数系教員や技術職の経験者の方たちを対象にSTEAM教育指導員セミナーを今年開催し、指導員の育成を行っている。
・今後、プログラミングの内容を学ぶ場も検討していく。
・引き続き、大学、企業等との連携や指導者の育成に努め、学校が必要とする人材の発掘や紹介を行い、学校の教育活動の支援を行っていく。
◎情報リテラシー教育について
課題
・スマートフォンやSNSの普及に伴い、インターネットの利用時間の長時間化やSNSを通じて児童が被害に遭ったり、個人情報が不正利用されるなど危険が増大している。
課題解決に向けた質問・提案
・これらの課題解決に対応するため、子どもたちに情報リテラシーを身につけさせることは重要。
・新学習指導要領にも情報モラル教育が位置づけられ、様々な教材が出ているが、全国一律的な教材や授業では進化し続ける教育のICT化に対応することが難しいため、専門の事業者にモラル教育を委託している自治体もある。
・世田谷区も教育のICT化を進める一方で、情報リテラシー教育を一層充実させる必要があると考える。
・現在の取組と今後の方針について、区の進捗状況について伺う。
成果
・今年度、デジタルシチズンシップの内容を教員研修に位置づけ、子どもたちを指導する教員がインターネットやソーシャルメディアとの適切な関わりについて学び、学級での指導にも生かすことができるように研修を実施した。
・昨今はネットによるいじめの問題も増えてきていることから、今月末にはネットいじめ防止研修を管理職や生活指導主任等を対象に行う予定になっている。
・ほかにも、インターネットトラブルから子どもを守るためのリーフレットを配布し、家庭において子どもと一緒にインターネットやスマートフォンのルールを定められるようにするとともに、ネットリテラシー醸成講座を各学校で開催し、子どもたちが正しく情報を活用できる力を高めている。
・引き続き、研修の実施や保護者への情報提供、ネットリテラシー醸成講座等を行っていくことで、情報リテラシー教育のさらなる充実を図っていく。
議会中継動画
定例会名
- 令和5年第2回定例会 一般質問
- 令和5年第1回定例会 予算委員会
- 令和5年第1回定例会 一般質問
- 令和4年第4回定例会 一般質問
- 令和4年第3回定例会 決算委員会
- 令和4年第3回定例会 一般質問
- 令和4年第2回定例会 一般質問
- 令和4年第1回定例会 予算委員会
- 令和4年第1回定例会 一般質問
- 令和3年第4回定例会 一般質問
- 令和3年第3回定例会 決算委員会
- 令和3年第3回定例会 一般質問
- 令和3年第2回定例会 一般質問
- 令和3年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第4回定例会 一般質問
- 令和2年第3回定例会 決算委員会
- 令和2年第3回定例会 一般質問
- 令和2年第2回定例会 一般質問
- 令和2年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第1回定例会 一般質問
- 令和元年第4回定例会 一般質問
- 令和元年第3回定例会 決算委員会
- 令和元年第2回定例会 一般質問
- 平成31年第1回定例会 予算委員会
- 平成31年第1回定例会 一般質問
- 平成30年第4回定例会 一般質問
- 平成30年第3回定例会 決算委員会
- 平成30年第3回定例会 一般質問
- 平成30年第2回定例会 一般質問
- 平成30年第1回定例会 予算委員会
- 平成30年第1回定例会 一般質問
- 平成29年第4回定例会 一般質問
- 平成29年第3回定例会 決算委員会
- 平成29年第3回定例会 一般質問
- 平成29年第2回定例会 一般質問
- 平成29年第1回定例会 予算委員会
- 平成29年第1回定例会 一般質問
- 平成28年第4回定例会 一般質問
- 平成28年第3回定例会 決算委員会
- 平成28年第3回定例会 一般質問
- 平成28年第2回定例会 一般質問
- 平成28年第1回定例会 予算委員会
- 平成28年第1回定例会 一般質問
- 平成27年第4回定例会 一般質問
- 平成27年第3回定例会 決算委員会
- 平成27年第3回定例会 一般質問
- 平成27年第2回定例会 一般質問
- 平成27年第1回定例会 予算委員会
- 平成27年第1回定例会 一般質問
- 平成26年第4回定例会 一般質問
- 平成26年第3回定例会 決算委員会
- 平成26年第3回定例会 一般質問
- 平成26年第2回定例会 一般質問
- 平成26年第1回定例会 予算委員会
- 平成26年第1回定例会 一般質問
- 平成25年第4回定例会 一般質問
- 平成25年第3回定例会 決算委員会
- 平成25年第3回定例会 一般質問
- 平成25年第2回定例会 一般質問
- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会
- 平成25年第1回定例会 一般質問
- 平成24年第4回定例会 一般質問
- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会
- 平成24年第2回定例会 一般質問
- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会






