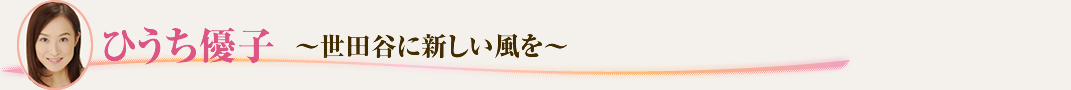
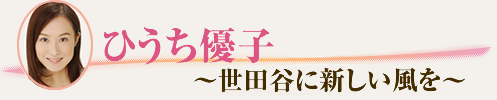
【その他】記事一覧
民族無形文化財『三土代会のお餅つき』




今週もイベントの連続。
今週初めは、代田八幡神社で行われている、三土代会のお餅つきに参加。
毎年参加させていただいております。
この三土代会の餅つき、餅のつきかたが独特で、古来より伝わる餅つき唄に合わせて、6-8人でつくのです。
民俗無形文化財に指定されています。
なんと5分でお餅がつけます!
実は、学生の時、ミス世田谷をしていた頃に、お仕事として携わって以来、毎年楽しみにしています。
日本の良き伝統文化を後世に伝えていくためには、毎年継続することが大切なのだ、と改めて思いました。コロナ禍で中止になったものの、私が学生の頃から続いている伝統行事。
このような日本の良き伝統を、後世に残す必要がある、と毎年実感しております。来年もよろしくお願いします。
年始から、新年会ラッシュ!

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
1月は新年会ラッシュです。今年の初新年会は、東京都行政書士会から!
私は行政書士でもあります。
年々、相続関係の法律相談が増えてまいりました。今年も皆様のお役に立ちたいと思います!
感謝 2024年大晦日




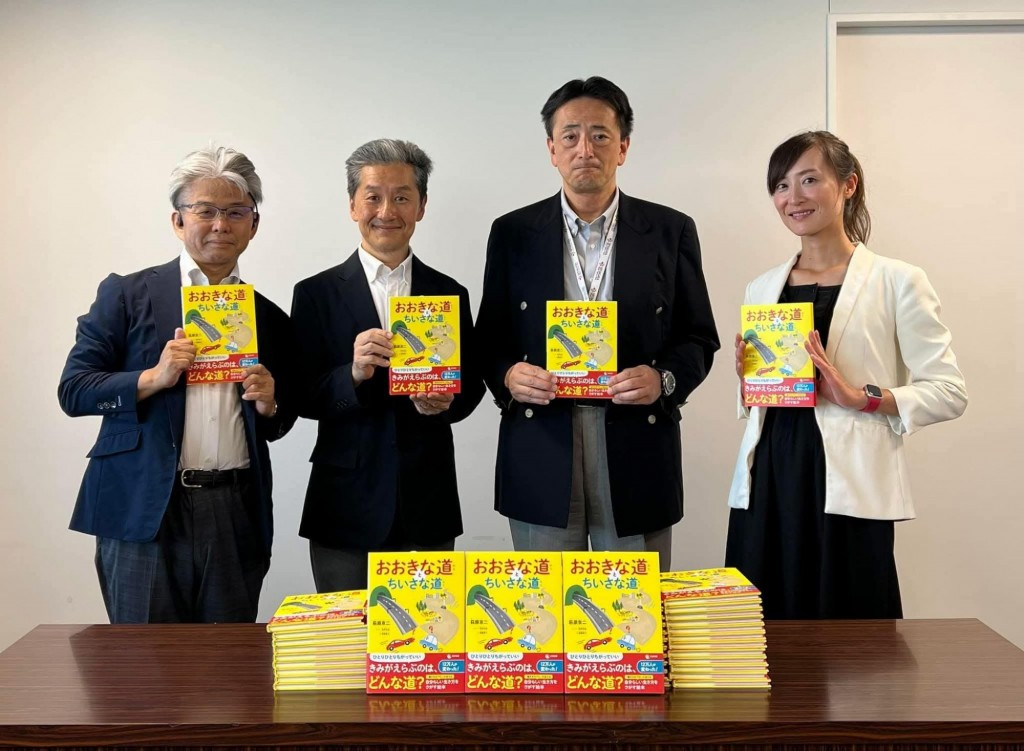


感謝
本年も1年間お世話になり、ありがとうございました。
今年を振り返って、まず、今年は、仕事と両親の介護の両立が大変な年でした。母が視覚障害者になり、父は身体障害者で、病院の送り迎え、食事の配達、介護サービスの手配、契約等……
でも、育ててもらった両親のために、できる限りのことをしたいと思っています。時間は有限です。
議員の仕事としては、
●新たな形の図書館、図書の宅配ボックス、ブックボックスの実現
●奥沢駅への図書館カウンターの実現
●自転車ヘルメット購入助成
●自転車専用レーンの整備
●土のうステーションの増設
●新公会計制度の活用
●せたがやpayと高齢者のお散歩ポイント連携
提案した政策が実現し、着実に前に進んでおります。
特に、図書館はブックボックスを始め、大きく前進しました!
このように政策実現できるのも、皆様のご支持あってこそ今がある、と実感した1年でした。
来年も皆様のお役に立つことができるよう、精一杯努力してまいります。また、これまでの取り組みもさらに前に進めてまいります。
初心を忘れることなく、これからも走り続けます。
引き続き、「ひうち優子」をご支援をいただけましたら、嬉しく思います。
では皆様、よいお年をお迎えください。
2024年 大晦日 ひうち優子
◎公園内へのドッグランの整備について
課題
・2022年に発表されたデータによると、日本で飼われている犬は約705万頭とのこと。
・住宅都市である世田谷区においては、かなり多くの方が犬をはじめ、ペットを飼っている。
・私のところに以前から「世田谷区内にはドッグランが少ない、公園にドッグランを増やしてほしい。」との声をいただく。
課題解決に向けた質問・提案
現在、駒沢公園、芦花公園にドッグランがあるが、新たな公園の中にドッグランを整備をしていただきたい。
前回からの進捗状況と今後について区の見解を伺う。
成果
・区内の公園では、都立駒沢公園と蘆花恒春園にドッグランが常設されており、区立では、野川緑道の一部で、区民団体である野川ドッグエリアの会が月2回程度、仮設のドッグエリアとして実施している。
・区立公園は都立公園に比べて面積も小さく、隣接する住宅までの距離が近いことから、常設のドッグランの設置が極めて厳しい状況。
・また、飼い主によるふん尿の放置や放し飼いによりほかの公園利用者が怖がる事例など様々な課題があり、公園の一部をドッグエリアとして使うためには、近隣住民や公園利用者の理解を得ることが必要と考えている。
・野川ドッグエリアの会では犬のしつけ教室や清掃活動を実施しており、区でも支援している。
・今後、ドッグエリアの運営を担う意向の団体が現れた際は、世田谷保健所と連携しながら、犬に関わる皆様が主体的かつ継続的にマナー向上に取り組んでいただき、近隣住民や公園利用者の理解を深めていただくよう協議するところから始めていく。
◎スポーツ施設の整備について
課題
以前から、私のところに、「世田谷区内のスポーツ施設がなかなか取れない。」
保護者の方からは、「子どものサッカークラブの毎週決まった練習の場所が欲しい、なかなか取れない。」と意見をいただいた。
課題解決に向けた質問・提案1
私の第一の希望は、世田谷区で新規のスポーツ施設を整備をしていただきたい。
何度か質問をしている、上用賀公園へのスポーツ施設の整備の進捗状況を伺う。
成果
・上用賀公園拡張事業は、現在、基本計画の策定に向けた検討を行っている。
・基本計画の骨子は、本施設の基本構想の基本方針を踏まえ、防災・安全、緑、スポーツの各要素の調和連携や、生涯スポーツ社会の実現を体現する公園、スポーツ施設といった取組方針やゾーニングの考え方を示した。
・また、スポーツ施設としては、区の防災拠点を兼ね備え、区民体育大会などの全区的なスポーツ大会の開催や、パラスポーツの拠点として中規模体育館と、屋外施設として球技での利用を想定した多目的広場を配置したところ。
・今後、基本計画(素案)の作成を経て、今年9月の基本計画策定を目指しており、引き続き新たなスポーツの場の整備に取り組んで行く。
課題解決に向けた質問・提案2
・私の第2の希望は、とはいえ都市部は地価が高いので、公共の土地だけでは限界がある。
・よってまずは公共施設の確保、難しい場合には民間事業者とも連携をして、スポーツ施設の場の確保について工夫をしていただきたい。
・また、私のところに、「幼児期にスポーツする場所がなかなかない、そのため児童館の体育館でバスケットをしていたが、靴を履かないように注意されてもめた、臨機応変に対応してほしい。そもそもスポーツをする上でシューズを履かないことについて、子どもの安全性の観点から問題ではないか、安全性に欠けている。」との意見をいただいた。見解を伺う。
成果
根本的な解決策として、幼児期からスポーツに親しむための環境づくりは、生涯を通じてスポーツに慣れ親しんでいくためにも重要であると認識している。
関係所管とも連携し、子どもたちが安全に安心してスポーツに親しみ、スポーツができる環境づくりに取り組んでいく。
◎区の施策へのゲーミフィケーションの活用
課題
世田谷区では、利用率が少ないイベントがある。
ゲーミフィケーションを活用した、他自治体の取り組み
・例えば、家庭での電気消費を減らす目的で、ゲームへの参加で外出を促すために、公共施設や商業施設などを目的地に設定をして、到着すると買物に使えるポイントや商業施設のクーポンなどを獲得できる取り組みがある。
・さいたま市や千葉市、横浜市などでは、マンホール聖戦と銘打って、マンホールの蓋を撮影して画像を投稿するとポイントを獲得するイベントには、553人が参加して、3万5000枚以上のマンホール画像が集まったため、10月には電柱も加えて追加イベントを開催したとのこと。
・府中市は、高齢者のフレイル予防を促す事業にゲーム要素を取り入れ、散歩の歩数を目的にして途中で撮影した画像を投稿するとコインがもらえる事業を始めたところ、65歳以上の219人の参加があった。
・佐倉市は、侍の町をテーマにしたゲームで、市内の歴史や民話に登場する神社や武家屋敷を実際に訪れると、佐倉市内の飲食店などのクーポンがもらえるなど、市内観光に役立っている。
課題解決に向けた質問・提案
・何時間も経過するほど熱中するゲームの要素を取り入れて、人々の行動変革を促すゲーミフィケーションを活用する自治体が近年急増している。
・世田谷区でも、例えば、昨年の第4回定例会で提案をしたサイクルツーリズムと結びつけて、自転車を利用して区民の健康増進や観光、そして地域振興に役立てるなど、せたがやPayを活用してゲーミフィケーションを要素として取り入れ、活用することを提案する。
成果
・例えば国民健康保険の加入者に対して、一定のチャレンジ期間に25万歩ウオーキングをすると、せたがやPayのポイントを進呈するというような取組を実施している。
・商店街の事業や観光、地域振興の分野では、商店や名所を巡るスタンプラリーだとか謎解きイベントを実施し、広い意味ではゲームを取り入れた取組をやっていると考えている。
・今後、例えば高齢者のフレイル予防の取り組みをゲーム的に楽しんでもらって、どうやって参加してもらうかというような話も、高齢福祉部と今話し合っている。
・観光や地域振興など、さきに挙げたような取組で、例えば民間事業者のゲーム的な取組と組むというようなことも考えられるので、今後も活用を図り、新たなアイデアも検討していきたい。
◎世田谷区生涯大学の見直しについて
課題
世田谷区生涯大学を利用されている区民の方から、次のようなご意見をいただいた。
「受講者が年々減ってきている。講師もコースも同じで、マンネリ化しており魅力が薄れている。高齢者が学べて仲間ができる生涯大学は貴重なので見直しをしてほしい。」
課題解決に向けた質問・提案1
・その後、私なりに世田谷区生涯大学について調べた。
・世田谷区生涯大学の最近の流れとして、コロナの影響もあるかと思うが、2020年度から2023年度にかけて毎年定員割れ、退学者増が続いており、受講者の減少の原因と改善を考えていく必要がある。
・まず、講師の任期に定めがないため、講師陣の長期委嘱と、講師の高齢化により新講師が現れない状況。
・また、コースも同じ内容でマンネリ化している状況。
・そこで、講師の任期の定め、新講師陣の発掘、コースのリニューアル、複数コースの選択化、二年のカリキュラムを一年間にするといった改善が必要と考える。
成果
・この大学の授業は、ゼミナール、文化講演会、健康体育活動及び移動教室と定められており、その中で主となるゼミナールは、社会、福祉、生活、文化Ⅰ、文化Ⅱの5コース。このコースは創設以来変わっていないが、その具体的内容、テーマは様々に設定をすることが可能。
・ゼミナールは、現在まで各講師により講座内容が固定化されている傾向もあるが、講師や講座内容は、毎年度の学生募集に向け、学長以下全講師と区で構成される運営会議において、その都度協議をして定めている。
・しかし、受講生の減少傾向はコロナ禍前から続いていたということも受け、今年度の運営会議において、改めてこの課題を確認し、令和7年度に向け、運営内容の見直しの検討を開始したところ。
課題解決に向けた質問・提案2
・2022年度に、これまでの生涯大学の受講者にアンケートを取っており、その中で受講者の方からは、同じ講師の同じコースが何年も続き、魅力がない、2年でなく1年のカリキュラムにすると講師も飽きなくてよいといった声がある。
しかし、せっかくアンケートを取っても、このアンケート結果が2023年度以降の運営方針に反映されていないということ。このような体制では改善できないと考える。
・アンケートの結果をしっかり反映して、第三者の視点を入れて生涯大学を運営していただきたいと考えるが、第三者の視点を入れることも含め、生涯大学の運営体制の改善について見解を伺う。
成果
・生涯大学では令和2年度より、コロナ禍に伴い、オンライン授業を開始するなど、特別体制となったので、令和4年度に受講生の意見を聴取することを目的にアンケートを実施した。
・その結果を受け、運営会議において受講生減少の課題の共有をしながら、一部のコースを対面授業に戻して申込数増加を果たすなど、改善を図ってきた。
・今回の見直し検討についても、運営会議において区から提案をして、協議の上、決定されたこと。
・大学の今後の発展に向け、事業内容等も含めて幅広く議論されるものと認識をして検討に当たりましては、受講生や卒業生のみならず、一般区民も対象に大学運営全般に関するアンケート調査を行うなど、客観性を高めて、より多くの区民に受講いただけるよう、生涯大学の見直し、改善を図っていく。
◎児童館での幼児のスポーツの場について
実現!
課題
代田南児童館を利用した保護者の方から、次のようなご意見をいただいた。
「幼児期にスポーツする場所がなかなかない。そのため児童館の体育館でバスケットをしていたが、靴を履かないように注意されてもめた。臨機応変に対応してほしい。そもそもスポーツをする上で、シューズを履かないことについて、子どもの安全性の観点から問題ではないか、安全性に欠けている。」
課題解決に向けた質問・提案
・代田南児童館のプレイルームは、スポーツができる環境が整っている。
・しかし、現在、児童館は靴を脱いで遊ぶ施設となっており、スポーツをするためには靴を履かないと危険で、スポーツをする子の安全性が担保できない。
・幼児がスポーツをする際には靴を履くよう改めていただきたいと考える。見解を伺う。
成果
・代田南児童館のプレイルームは、体を動かした様々な遊び等、多目的に利用できる施設となって、靴を履いた児童と履かない児童が一緒に活動することは、履かない児童のけが等につながるおそれがあることから、原則として靴を履かないこととしている。
・ご指摘のとおり、スポーツを行う際には、靴を履かないとかえって危険になることもあるため、例えば中高生全員が靴を履いて利用する場合など、状況に応じて靴を履いて利用するケースもある。
・代田南児童館のプレイルームにおいても、利用者の安全を確保するため、原則としては靴を脱いでの利用とするが、他の利用者がいないときなど、危険が回避できる場合は、靴を履いての利用を認めるなど、子どもの願いに寄り添った柔軟な運営に努めていく。
◎介護ロボットの導入について
課題
・介護現場で、人手が足りない現状がある。
・1人暮らしの高齢者のコミュニケーション不足という現実がある。
課題解決に向けた質問・提案
・令和4年3月の定例会で、コロナ禍における特別養護老人ホームなどでのコミュニケーションの手段として、人型ロボットの導入を提案した。
・介護施設での人型ロボットには、介護をする方の腰の負担を軽減するための車椅子への移乗支援や、介助者による抱え上げ動作のパワーアシストなどがあり、今後、介護分野での人手不足に有効と考える。
・自宅での介護ロボット導入については、自立支援型や見守り型の在宅向け介護ロボットがある。これらは、高齢者の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレの往復やトイレの姿勢維持を支援する歩行支援機器といった移動支援、また排せつ物処理やトイレ誘導、動作支援といった排せつ支援のほか、見守りコミュニケーションや自宅での入浴支援などがあり、在宅の要介護高齢者にとって必要なツールと考える。
・世田谷区として導入支援をしていただきたいと考える。見解を伺う。
成果
・在宅向け介護ロボットは、自立支援型の場合は要介護高齢者の自宅内での移動等を支えるものであり、また見守り型の場合は、高齢者への見守りやコミュニケーションの維持に資するものであり、いずれも要介護高齢者等が在宅生活を継続する上で、貴重なツールであると認識している。
・特に見守り型は、区がこれまで実施してきた高齢者への見守りの取組のさらなる充実に向けた具体策として、デジタル技術を活用した見守りが有効であると考えており、介護ロボットはその一つの手法。
・現在、第九期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向けた議論が始まったところであり、DXの推進という視点も踏まえ、今後、高齢・介護部会において在宅向け介護ロボットに関する議論も進めていく。
◎介護ロボットの相談窓口設置について
課題
介護現場では、人手不足が深刻との声を聞く。
課題解決に向けた質問・提案
・厚生労働省は、2023年度から介護事業者からの介護ロボットをはじめとしたICT機器の導入などの業務効率化に関する相談をワンストップで受け付ける窓口の設置を希望する自治体を募集する。
・運営は民間事業者などに委託することが可能で、事業費の3分の2を国が補助するとのこと。
・私は、令和4年3月の定例会で、コロナ禍における特別養護老人ホームでのコミュニケーション手段として、人型ロボットの導入を提案したが、ほかにも高齢者の移乗支援としてのパワーアシストや歩行アシストカート、自動排せつ装置や見守りセンサーなども補助の対象になるということ。
・ICT機器を開発している知り合いの方に聞いたところ、民間では既に、介護ロボットをはじめ見守りシステムなど、介護施設などで使用すればかなりの介護者の負担が軽減できるICT機器が実用化されているにもかかわらず、区役所の担当窓口に紹介をしても、介護事業者との仲介をしてもらえない現状があるとのこと。
・国の介護ロボットに関する相談窓口の設置に関する自治体向けの支援は都道府県向けであり、東京都では既に東京都福祉保健財団に委託、補助を行っている。
・そこで、事業者への周知を行っていただき、事業者の介護ロボット導入に向けて支援をしていただきたい。見解を伺う。
成果
・国では、令和5年度より介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等、生産性向上に資する様々な支援を一括して取り扱い、事業者へのワンストップ型の支援を可能とするために、事業者向けの介護ロボット等に係る相談窓口を設置した場合等の都道府県に対する支援を拡充するとしている。
・東京都は既に先行して実施しており、都が公益財団法人東京都福祉保健財団に委託及び補助して、事業者向けの対面やオンラインによる相談窓口を設置している。・一方で、このような窓口が設置されていることをまだ知らない事業者も多くいるので、区として、今後、都の相談窓口の周知に努める。
議会中継動画
定例会名
- 令和5年第2回定例会 一般質問
- 令和5年第1回定例会 予算委員会
- 令和5年第1回定例会 一般質問
- 令和4年第4回定例会 一般質問
- 令和4年第3回定例会 決算委員会
- 令和4年第3回定例会 一般質問
- 令和4年第2回定例会 一般質問
- 令和4年第1回定例会 予算委員会
- 令和4年第1回定例会 一般質問
- 令和3年第4回定例会 一般質問
- 令和3年第3回定例会 決算委員会
- 令和3年第3回定例会 一般質問
- 令和3年第2回定例会 一般質問
- 令和3年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第4回定例会 一般質問
- 令和2年第3回定例会 決算委員会
- 令和2年第3回定例会 一般質問
- 令和2年第2回定例会 一般質問
- 令和2年第1回定例会 予算委員会
- 令和2年第1回定例会 一般質問
- 令和元年第4回定例会 一般質問
- 令和元年第3回定例会 決算委員会
- 令和元年第2回定例会 一般質問
- 平成31年第1回定例会 予算委員会
- 平成31年第1回定例会 一般質問
- 平成30年第4回定例会 一般質問
- 平成30年第3回定例会 決算委員会
- 平成30年第3回定例会 一般質問
- 平成30年第2回定例会 一般質問
- 平成30年第1回定例会 予算委員会
- 平成30年第1回定例会 一般質問
- 平成29年第4回定例会 一般質問
- 平成29年第3回定例会 決算委員会
- 平成29年第3回定例会 一般質問
- 平成29年第2回定例会 一般質問
- 平成29年第1回定例会 予算委員会
- 平成29年第1回定例会 一般質問
- 平成28年第4回定例会 一般質問
- 平成28年第3回定例会 決算委員会
- 平成28年第3回定例会 一般質問
- 平成28年第2回定例会 一般質問
- 平成28年第1回定例会 予算委員会
- 平成28年第1回定例会 一般質問
- 平成27年第4回定例会 一般質問
- 平成27年第3回定例会 決算委員会
- 平成27年第3回定例会 一般質問
- 平成27年第2回定例会 一般質問
- 平成27年第1回定例会 予算委員会
- 平成27年第1回定例会 一般質問
- 平成26年第4回定例会 一般質問
- 平成26年第3回定例会 決算委員会
- 平成26年第3回定例会 一般質問
- 平成26年第2回定例会 一般質問
- 平成26年第1回定例会 予算委員会
- 平成26年第1回定例会 一般質問
- 平成25年第4回定例会 一般質問
- 平成25年第3回定例会 決算委員会
- 平成25年第3回定例会 一般質問
- 平成25年第2回定例会 一般質問
- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会
- 平成25年第1回定例会 一般質問
- 平成24年第4回定例会 一般質問
- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会
- 平成24年第2回定例会 一般質問
- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会


